|
≫ガブリエルの影 Lords of Exile
|
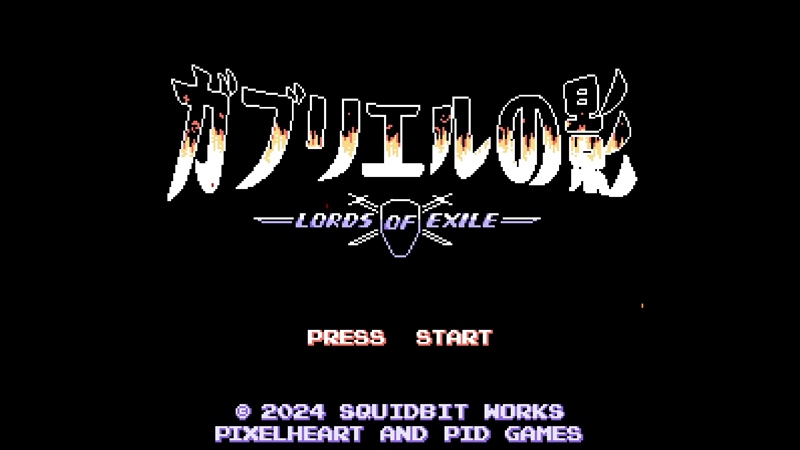
■発売元:PID Games、PixelHeart、Dear Villagers、Plug In Digital /
■開発:Squidbit Works /
■ジャンル:アクション /
■IARC:12歳以上対象(軽度の暴力描写あり) /
■定価:1,700円(税込)
◆公式サイト / ストアページ
≫Lords of Exile(Steam)
©2024 Squidbit Works / PixelHeart and PID Games
|
|
▼Information
|
|
■プレイ人数:1人 /
■セーブデータ数:1つ /
■推定クリア時間:2~2時間半
|
戦乱に包まれた極東の地「エクシリア」。「弱者は強者によって支配されるべし」の思想を持つ騎士「ガブリエル」は、主君である怒れる王「ガラガー」直属の処刑人として、何千もの人々の命を奪ってきた。
しかし、その度を超えたガブリエルの残虐性にガラガーはいつしか恐怖を抱くようになる。そしてガラガーは、ガブリエルへの戒めと警告を意図して、彼の愛しのフィアンセを殺害するに至った。

だが、結果としてこれはガブリエルの逆鱗に触れることになってしまう。そしてガブリエルは、自らの行いと思想がフィアンセの命を奪う事態を招いたという罪を背負う形でガラガーの打倒を誓う。
かくして、血を血で洗う復讐劇の幕が開ける。
|
|
▼Pros cons Pick up
|
--- Good Point ---
◆不確定要素を控え目とし、トライ&エラーによる着実な上達とその楽しさが凝縮された難易度
◆残機制なしの現代仕様ながら、それを免罪符に陰湿な罠などを設けないスタンスが徹底されたステージ構成
◆少ない色数を巧みに活かし、細部まで描き込む技が炸裂した見応え十分のグラフィック
◆まさに「血が湧き、肉が躍る」を体現するかの如し熱さと臨場感に秀でた音楽
◆歩行速度こそ遅めながら、攻撃を始めとする動作は軽快で手触りの良さが押さえられている操作周り
◆往年の名作アクションゲームらしさ全開の1本道構成に徹した本編構成およびゲームデザイン全般
◆単純かつ王道な1本道構成に変化を付けると同時に、進める楽しさを引き立てる「スキル」システム
◆往年の名作アクションゲームらしさ全開の個性豊かで、時に見た目の派手さでも楽しませてくれるボス戦
◆1周約2~2時間半のいかにも往年のアクションゲームらしい程好さが光るボリューム
◆「スピードラン」「ボスラッシュ」、そして追加キャラによる2周目とそれなりに押さえられたやり込み要素
◆攻撃ヒット時の効果音、ボス撃破時の派手な爆発など、古き良き味が表現された演出
--- Bad Point ---
◆“悪魔城”および“ステインド”のオマージュ感の強さも否めないゲームデザイン(特に後者)
◆溜め操作必須に加え、使用の機会もゲーム側に強制されている感が否めない練り込み不足の「影」システム
◆特にクセがある訳ではないが、人によっては気に障る側面を持ったガブリエルのゆったりとした歩行速度
◆不確定要素による理不尽さは皆無とは言え、初見殺しな罠はそれなりの各ステージ(特に後半)
◆8ビット風という売り文句と著しく矛盾した音楽(8ビットというよりは、8×2ビット風が正確なところ)
◆同じく8ビット風という売り文句との矛盾した、多重スクロール表現なども含めたグラフィック
◆文章とカーソルの表示位置が著しくズレているのを始めとする日本語ローカライズ周りの雑さ
|
|
▼Game Overview
|
強者たる戦士よ、慈悲なき復讐を成せ
◇スペインを拠点に活動する独立系スタジオ「Squidbit Works」制作による横スクロール型アクションゲーム。PC以外にもPlayStation 5/4、Nintendo Switch、Xboxプラットフォーム(Series X|S、One)版も展開されている。また、本編の一部楽曲は『イース』『アクトレイザー』『世界樹の迷宮』などで知られる古代祐三氏が手がけている。
アクションゲームとしてはステージクリア型。主人公の「ガブリエル」を操作し、仇敵ガラガーとその王国の打倒を目指し、全8つのステージ(作中表記は「レベル」)の攻略に挑む。本編は、1980年代から1990年代前半に見られた古典的な横スクロールアクションゲームを踏襲した1本道構成で展開される。そのため、一度クリアしたステージへの再訪はできない。各ステージのクリア条件も最後に待ち受けるボスを倒すという、これまた当時のアクションゲームを踏襲したものになっている。
◇プレイヤーの操作するガブリエルの特徴としては、歩行速度の遅さがひとつとしてあげられる。そのため、アクションゲーム全体のテンポはゆったりとしている。反面、歩行速度以外の攻撃については対応するボタンを押せば瞬時に繰り出せる仕組み。アクション自体も豊富で、基本の歩行と斬撃のほかにスライディング、下突き、金網を掴んでの全方位移動などが用意されている。また、ステージクリア時の「スキル」獲得に応じてアクションが増えるという要素もある。スキルに関係する代表的なアクションとしては二段ジャンプがある。ほかに斬撃のパワーアップなどもあり、基本的に本編が進むほどガブリエルは強くなると同時に、できることも増えていく特徴を持ち合わせたプレイヤーキャラクターとして設計されている。
◇「スキル」とは別に「影」と称される能力も用意されている。これは特定のステージの節目に設けられた「ナオコの修行」を乗り越えることによってガブリエルが獲得。画面左上に表示された体力ゲージ下の「呪いゲージ」が満タンになった時、対応するボタンを押すことによってガブリエルの背後に戦いをサポートする「影」(幽霊?)のようなキャラクターを召喚できる。漫画『ジョジョの奇妙な冒険』の第三部以降の象徴的な要素として知られる「幽波紋(スタンド)」みたいなもの、と言えばピンとくるかと思う。というか、キャラクター自体が霊体なので、モロにスタンドそのものである。
基本的に影は攻撃ボタンを長押しすることにより、それぞれが持つ技を繰り出してくれる。「カツ」ならば特定のブロックを破壊する衝撃波、「シンセク」なら特定の柱に突き刺してガブリエルをそちら側へと引き寄せるチェーンフックを放つといった具合。
◇「影」の技を使うと「呪いゲージ」は減少する。もし、そのままゲージが空になってしまえば、影はガブリエルの背後から消え、それぞれが持つ技も使えなくなってしまう。ただし、「呪いゲージ」自体は自動で回復する仕組みとなっているため、その場である程度、待っていれば再び召喚することは可能。自動回復とは別にゲージを満タンにするアイテムも存在。主に道中で手に入るようになっている。なので、あまりゲージのやりくりを意識する必要もなく直感的に使っていける設計である。
◇このほか、ガブリエルはメインの剣以外にサブ武器も用意されている。「サブ武器」は関連するアイテムを道中で手に入れることが必須。また、サブ武器は基本的に有限式であるため、延々と使うことはできない。逆に基本の剣による斬撃と組み合わせ、適切な場面で使うことを心がければ、より安全かつ的確にステージを進めていくことが可能だ。
全体的にアクションゲームとしては古典的ではあるが、「スキル」と「影」という進行に応じてキャラクター性能が上昇していくシステムの存在によって現代的な遊び心地を表現。残機制も採用していないため、途中でやられてしまってもチェックポイントからの再開が可能と難易度も良心的な方向性でまとめられており、懐かしさと新しさの両立を強く意識した内容に仕上げられている。
|
|
▼Review
≪Latest Update :11/23/2025 | First Publication Date:11/23/2025≫
|
|
「パターンゲー」としての魅力と醍醐味を徹頭徹尾表現しきった良作。
|
1980年代から1990年代前半に見られた名作アクションゲームに影響を受けて作られた新作というのはインディーゲームの界隈では頻繁に見られるものである。正直なところ、本作もその一角に当たるタイトルであるのは否定しない。
ただ、「パターンゲー」としての魅力と醍醐味を貫き通し、楽しい高難易度を表現し尽くしている点で一線を画す仕上がりである。いわゆるその手のインディのアクションゲームというのは、残機制を採用しないことによる現代的な遊び心地を表現することもひとつの定石になっている。
しかし偏見かもしれないが、そういう残機制を廃した作品に限って難易度を不当なまでに高く設定する傾向もよく見られる。ゲームオーバーによって大きく巻き戻されてしまう心理的な不安とストレスがないのを免罪符に、道中に沢山の一発アウトな仕掛けを設けたり、敵の配置を初見では到底対処不能なものにする、陰湿な攻撃や動きを決めてくる敵をまとめて登場させるというのが一例である。無論、中にはそんなことをせずに真っ当に楽しい高難易度を表現している作品もある。しかし、「残機制がないから、好き放題難所を作ってしまえ」という軽い気持ちでやり過ぎてしまっている作品があるのも事実。
そんな一例がある中での本作は、残機制無しを免罪符とせず、1980年代から1990年代前半の古典的な名作アクションゲームたちが持っていた“楽しい高難易度”の表現に徹している。
特に素晴らしいのが道中からボス戦に至るまで、「パターンゲー」としてのバランスを堅持していることだ。思いがけない場所からいきなり敵が現れたり、攻撃の順序を崩して迫ってくるみたいな不確定要素が少なく、すべてがあらかじめ決められたパターンに沿って構築されているので、トライ&エラーを重ねるほど分かりやすいぐらいプレイヤーの動きが洗練されてくる。
そのおかげもあって、ほぼすべてのステージとボスが無傷(ノーダメージ)による突破が可能どころか、その余裕すら生まれる可能性を持った作りになっているのである。「パターンゲー」というのは、トライ&エラーを重ねるたびにプレイヤー自身の動きが洗練され、カッコイイ立ち回りが自然にできるようになっていく快感が醍醐味だ。本作はそれを完璧に近いレベルで押さえていて、上達することによる嬉しさと気持ちよさをこれでもかと言わんばかりに提供するのである。
しかも、前述したように不確定要素も少ないので、プレイヤー側が「ふざけるな!」と暴言を衝動的に吐きたくなってしまう陰湿さのあるシチュエーションも少ない。ごく一部、初見時にドッキリさせられる場面もあるにはあるが、何回か取り組むうちに「そんなにヤバいものか?」との感想が勝るようになるものに設計されている。そして、これを終始、ステージのみならずラスボスにまで一貫してやっているのも特筆に値する。終盤になるとさすがに厄介な動き方で攻めてきたり、倒すのにコツが要る敵も出てくるのだが、いずれも被害を最小限に抑え込める隙があるので、何度か対決を重ねるたびに脅威度合いも下がってくる。
ボスにしても全個体がちゃんとパターン化できるので、戦っていて純粋に楽しい。一部、ツッコミ不可避の安全地帯が設けられたボスもいるのだが、それが逆に往年のアクションゲームらしさを引き立てていたりするのが面白いところだ。
残機制がない設計には、それを免罪符にした嫌らしさがてんこ盛りなアクションゲームであること想像させ、先入観を抱かせてしまう側面がある。だが、実際は真っ当にパターンゲーとしての遊び応えと楽しさを貫き通している。「何をするんだ!」と初回には物申したくなる敵やボスも、やればやるほどに「かかってこいやーッ!」と強気に出て倒せる存在へと変貌する展開が目白押し。まさにこれぞ「パターンゲー」にして、楽しくてやさしさすらある高難易度だと実感できる魅力が本作には凝縮されているのだ。
グラフィックなどの見た目やストーリーからは微塵もそんな雰囲気を感じさせないが、触れてみれば嫌というほど思い知らされる。特にアクションゲーム好きならば、本作のこの作りには色んな意味で「わかってらっしゃる」と首を深々と下げたくなるだろう。
|
アクションゲームの要とも言える操作性も非常によく、特に各種アクションは、ガブリエルのゆったりとした歩行速度を思わせない手触りの良さがある。攻撃が敵にヒットした際、派手で小気味よい効果音が鳴り響く演出面の配慮もバッチリだ。
演出に関しては、道中で対峙する雑魚敵やボスの散り様も派手なものになっていて、それぞれ倒した時の爽快感を引き立てる。グラフィックについても、特にファミリーコンピュータ(ファミコン)の後期作品を彷彿とさせる色数少なめながら、細かく描き込まれたドット絵が異彩を放つ仕上がり。主に背景周りは、その魅力が存分に発揮されているので必見である。
それらのグラフィックをバックに流れる音楽も、これぞアクションゲームと言わんばかりにキャッチーでテンションを上げる楽曲揃い。前述したように、一部の楽曲は古代祐三氏が担当しているのだが、他の作曲陣も『Gravity Circuit(グラビティ サーキット)』などで音楽を担当したDominic Ninmark(ドミニク・ニンマーク)氏、『Nuclear Blaze(ニュークリア・ブレイズ)』などの音楽を担当したPentadrangle(ペンタドラングル)氏と実力派が揃っている。
個人的にイチオシはドミニク氏が手がけた楽曲で、その中でも本編後半のとあるステージの曲「Twilight's Edge」は、まさに「血沸き肉が躍る」の表現がこれ以上なく似合う仕上がりとなっているので要チェックだ。ペンタドラングル氏も最初のステージの曲である「Outcast Overture」を始め、素晴らしい楽曲揃いなので、こちらも並行して要チェックである。なお、Steamではサウンドトラックも販売中である。曲がお気に召したらぜひこちらを。
ただ、音楽に関してはトレイラーを確認すれば分かる通り、グラフィックとの不一致に違和感を抱くかもしれない。見た目はファミコンを思わせる8ビット調なのに、音楽はバリバリの16ビット調(FM音源風)であるためだ。人によっては「ちゃんとグラフィックに合った音源にしろよ!」と物申したくなるのは不可避。
正直、この点はよくも悪くもインディーゲームらしいと言える。ちなみにグラフィックにおいても、一部ステージで多重スクロールの表現があるといったそれっぽくない部分があったりする。まあ、多重スクロールについては、現実のファミコンにも『ロックマン6 史上最大の戦い!!』などの多重スクロールを表現した作品があったりするので、ギリギリ“らしさ”はあると言えるのだが。
本編のボリュームは1周およそ2時間ほどで、1980年代から1990年代前半の名作アクションゲーム(具体的には1本道構成の作品)と大差ない規模。ただ、クリア後のやり込み要素として「スピードランモード」「ボスラッシュモード」が用意されているため、すべての要素をやり尽くすとなればそれ以上の時間を攻略に要すことになる。
また、少々ネタバレになるが、クリア後にはガブリエルとは異なる性質を持った第2のキャラクター「リリア」が解禁され、それによる2周目が楽しめるようになる特典もある。“ガブリエルとは異なる性質”の通り、移動が早かったり、メイン攻撃が遠距離であるなど、手触りの異なるアクションゲームへと変貌する特色と魅力を持っているので、気になればぜひチャレンジを。
全体的に1980年代から1990年代前半の名作アクションゲームの良さ、特に「パターンゲー」の醍醐味がしっかりと押さえられた良作に仕上げられている。ただ、惜しい部分も少なからずある。特に「影」を使ったアクションについては、ステージの構造もあって「使用を強制されている」と実感させられる側面が強く、十分に活かしきれていない。各種技についても溜め操作を前提にしている関係から使い勝手の悪さが否めず、場面によっては進行テンポを損ねる要素と機能してしまっているのが残念。
それから日本語ローカライズの雑さ。文章の翻訳自体は及第点で、文字フォントもドット調でグラフィックの雰囲気とマッチしているのだが、表示位置が露骨なまでにズレてしまっていて、非常に見栄えの悪いものになってしまっている。日本語がこれならほかの言語も……と思いきや、ほかの言語はなんら問題がない感じで、完全に実装時の調整漏れであることが露見している感じだ。
一応、ゲーム本編のプレイに当たっては特に支障はないのだが、正直、気にしないのにも無理があるほどのズレっぷりなので、アップデートで正されることを望むばかりである。まあ、発売から1年以上経った2025年のいまでも無修正のままなのだが。
以上のような残念な箇所もあるが、良作であるのは確か。アクションゲーム好きならばぜひ触れてみていただきたい作品である。音楽もグラフィックとはミスマッチながら、「細かいことは気にするな!」と力でねじ伏せられてしまうほど熱い楽曲が揃っているので、それ目的でプレイしてみるのもよし。雰囲気は殺伐としているが、実は結構“やさしい”復讐劇に身を投じよう。
|
|
≫トップに戻る≪
|